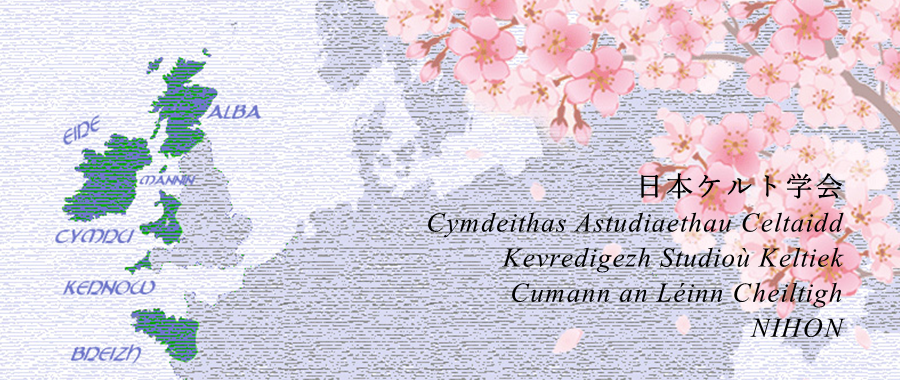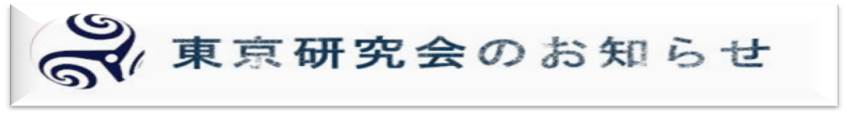日本ケルト学会の公式ホームページです。
「ケルト学」は古代ギリシャ・ローマの文献で「ケルト人」「ガリア人」などと呼ばれる人々に関連する研究、および18世紀に新しい言語学上の分類名称として登場した「ケルト語」を共通項とする諸地域(アイルランド、スコットランド、ウェールズ、マン島、コーンウォール、ブルターニュ)に関連する諸学の集合体です。ケルト学の研究分野は言語学、文学、文献学、社会学、歴史学、考古学、人類学、民俗学、政治学、美術、音楽などの多方面に及びます。日本ケルト学会はこれらケルト学の諸分野における研究および成果の紹介を推進する一方で、欧米のケルト学やケルト概念の歴史的・批判的検討、さらにはケルト諸語地域の文化と日本文化との比較研究等を行っています。
主な活動としては研究会、研究大会開催のほか、会員向けに「ニューズレター」(年2回発行)、学会誌『ケルティック・フォーラム』(年1回発行)を配布しています。